インボイス(適格請求書)とは?インボイス制度に対応した領収書の書き方や扱いについても解説します!
今からでも遅くない!インボイスに関する疑問を解消!
本記事では、2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)について、インボイス制度の概要から制度導入後にどうしたらよいかなどを解説します!
お客様の活用事例や印刷・集客のノウハウなどお役立ち情報
最新記事一覧

年賀状には干支をモチーフにしたイラストや文字があると、年の初めに明るい未来や動物のもつ縁起のよさを感じられます。2024年は、辰年です。 この記事では、年賀状を作る前に知っておきたい、2024年の干支と十二支の意味について解説します。

この数年、コロナ禍によって社会やビジネスの在り方は大きく様変わりしました。特に医療現場では、情勢が目まぐるしく変化し、厳しい状況が今なお続いています。製薬企業様にとっては対面接触が難しくなったのに加え、リモートワークの推奨などから、支店や営業所においても従来のやり方や発想とは大きく異なる事業活動が求められるようになってきました。
そうした状況下において、MRの皆様からは「医師の先生方との接点を持つのが非常に難しくなった」「新たな手立てを模索しているが、なかなか効果的なやり方がわからない」といったお悩みが聞かれるようになってきました。また、従来はオフラインで開催していたセミナーや講演会をWeb上で行ったり、リモートワークをしながら案内状の制作や発送をしたりするなど、以前にはなかった業務上の課題にお困りの方も増えています。
そこで、このたびラクスル株式会社では、医療分野に置けるAI開発やWeb講演会運営の配信実績でシェアトップを誇る木村情報技術株式会社様と共催で、製薬企業様向けのオンラインセミナー「医師との接点の作り方」を開催。『呼ばれるMR大全』の著者でもある木村情報技術社のコンサナリスト®事業部長の川越 満氏から、コロナ禍におけるMR活動の工夫のご紹介、参加者の皆様からのご質問やお悩みに回答いただきました。また、ラクスル事業本部 エンタープライズ事業部の川並 拓樹からは、セミナーや講演会の案内状関連業務の負担を軽減する「セミナー案内状リモート印刷サービス」をご紹介。コロナ禍におけるMRの皆さんの活動を支援する有意義な情報をお届けしました。

店舗のオープン・再開やキャンペーンに合わせ、複数の印刷商品を組み合わせて店舗販促を成功させましょう!

リード獲得、商談、お客様フォローと営業活動は続きますが、目的や利用シーンに応じた販促物の企画・作成が大切です。 当記事では、営業のシーン別によく使われている印刷商品をご紹介いたします。
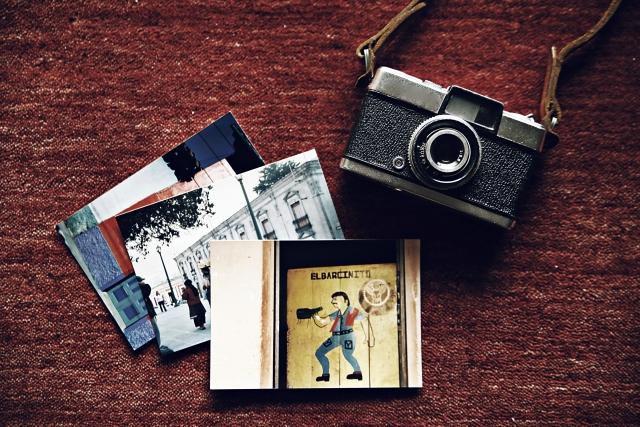
一般的な写真サイズとされる「L判」の大きさは「89×127mm」です。自身が撮影した写真をL判で印刷したところ、端まで印刷されずに困った経験がある方も多いでしょう。 そこで本記事では、L判を端まで印刷する方法や注意点などについて紹介します。

ページ数が多い印刷物は、印刷した用紙を順番どおりに並べ、製本する必要があります。この並びどおりに用紙を取り上げる作業を「丁合」または「丁合取り」というのです。この記事では、丁合の手法や丁合機のしくみ、関連する用語について詳しく解説します。

印刷物は、元になる版のしくみや条件によって仕上がりのクオリティが大きく変わります。オフセット印刷やインクジェットプリンターでの印刷などで「条件」にあたるのがスクリーン線数です。この記事は、印刷におけるスクリーン線数と使い分けの例について解説します。

印刷物の製本方法である短辺綴じとは、短い辺で綴じることを指します。短辺綴じは、使い方次第で内容を魅力的に制作できます。この記事では、メリットやデメリットとともに、ほかの綴じ方についても解説します。

印刷方法は大きく分けると、有版式と無版式の2種類です。有版式はさらに4種類に分けられ、印刷方法によって仕上がりや特徴が異なります。この記事では、印刷方法の種類について解説します。使い分ける際のポイントを参考に、適した印刷方法を選択しましょう。

印刷物に施せる加工の種類は8つです。用途に合わせて使い分ける必要があります。使い分けるには、それぞれの加工について知っておきましょう。この記事では、印刷物に施せる加工の種類について解説します。おすすめの印刷方法についても触れます。

プロモーションの告知や新商品の宣伝など、活用の幅が広いのが店舗ポスターです。しかし店舗ポスターのデザインを自前で作成する際は、そのコツや注意点をおさえておかなければなりません。 そこで当記事では、店舗ポスターのデザインを作成する4つのコツと注意点などを解説します。

営業効果の高いパンフレットを作るには、利用シーンを明確にするなどのコツをおさえておかなければなりません。またコツをおさえるだけではなく、用途に応じた仕様を選ぶことも大切です。 そこで当記事では、営業パンフレットの効果を高めるための3つのコツとおすすめの仕様を紹介します。

ハガキは電子メールの普及で利用頻度が減少しつつあるものの、ビジネスツールとしてはいまだ欠かせないアイテムの1つです。ただしプライベートで送りあうことの少ない現代において、文章の基本が分からないといった方も多いでしょう。 当記事ではビジネスで利用するハガキの4つの基本と留意すべき表現について紹介します。

企業の顔として多くの取引先に足を運ぶ営業。そんな営業で必須アイテムなのが名刺です。特に初めて訪問する企業においては、担当者と名刺交換を行わなければいけません。そこで今回は、営業の名刺カードを作成するときのポイントや記載すべき必要項目について紹介します。

印刷物にはさまざまなサイズと形式があります。その中でも、用途の広さから印刷物やグッズなどで利用されているのが冊子です。冊子は手軽に見たり読んだりできて持ち運びにも便利なので、企業の商品カタログやノベルティグッズとしても活用されています。冊子のサイズの種類や制作費用などについて紹介します。

ブックレットとは、いったいどのような冊子のことでしょうか。パンフレットやリーフレットといった、ほかの冊子との違いがわからない人もいるでしょう。 この記事では、ブックレットの基礎知識やほかの冊子との違いを紹介します。ブックレットの作成方法や作成する際の注意点も併せて紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

ポストカードとは、いわゆる「郵便で送ることができるハガキ全て」を指します。官製ハガキだけでなくさまざまな材質や大きさがあり、それぞれ郵便料金やルールがあることには注意が必要です。ここでは、ポストカードの大きさと、注意すべきポイントを解説します。

企業にとって新しい商品やサービスを世間に広く知らしめる展示会は、特に力の入る一大イベントです。中でも非常に重要な告知ツールが「ポスター」。しかし、何もないところから「作れ」といわれても、戸惑う方もいるでしょう。 この記事では、これから展示会ポスターを企画・制作する方に向けて、展示会用のポスターの役割と重要になる要素を解説します。

和紙シールとは、どのような特徴があるかご存じでしょうか。和紙という素朴な風合いを活用した和紙シールは、一般的な用紙とは違った魅力を持っており、商品ラベルやロゴマーク、ワンポイントシールなどに活用されているのです。 この記事では和紙シールの特徴や用途を解説します。和紙にはさまざまな種類があるため、製品に合わせた和紙シールを作成し、製品の魅力を引き出しましょう。
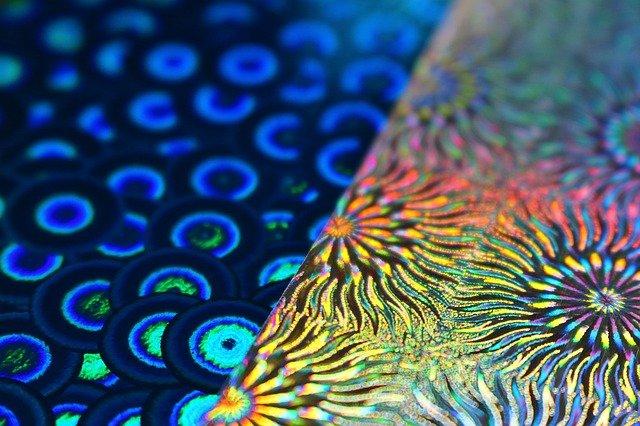
ホログラムシールにはノベルティや偽造防止など、さまざまな用途があります。自分でデザインしたホログラムシールを作る際は、どのようなオプションをつけられるかを知っておくと便利です。 そこで今回は、ホログラムシールの種類や用途を解説し、印刷の際に使えるオプションを紹介します。
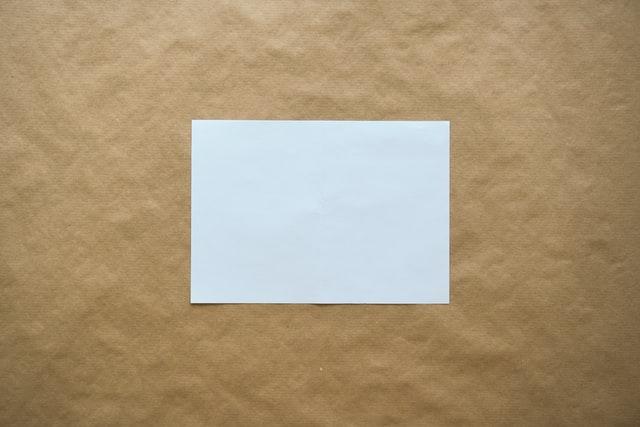
もしもあなたが学習塾の経営者や塾講師であるならば、名刺を持つことをおすすめします。なぜなら、初対面の保護者や生徒から信頼を得られやすくなるためです。 ただし、ただ単に作るのではなく、デザインやサイズを選び、信頼感を与えられるような名刺であることが望ましいでしょう。本記事では学習塾で名刺を作成する際のコツと、おすすめのサイズ3つを紹介します。

不動産に関連する業務の中では、請求書や納品書などの書類を扱う場面が頻繁にあります。その中でも封筒は使い方によって、自社の宣伝につながることは意外と知られていません。 そこでこの記事では、不動産業務で需要の多い封筒や封筒作成時のオプション、おすすめの用紙種類などを紹介します。

近年、新規顧客の獲得やお店の宣伝になることを期待して、名刺(ショップカード)を作る飲食店が増加しています。ただ、飲食店での名刺作成が本当に必要なのか悩む人もいるでしょう。 そこで今回は、飲食店の名刺をなぜ作るのか、ショップカードを作る際に何を載せたらいいのかなど、お店の名刺を作るメリットや記載したい情報を見ていきます。
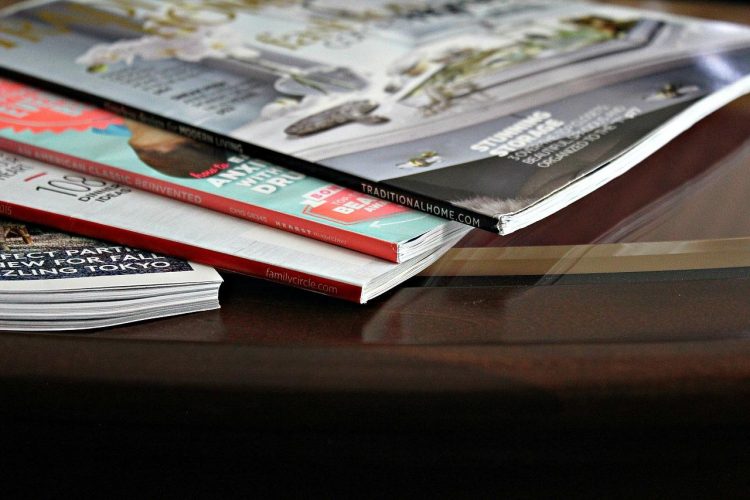
不動産業界にとってパンフレットは、契約の決め手ともなる重要な販促ツール。販促ツールに工夫を凝らすかどうかで、売上が大きく変わる業界でもあります。不動産業界にとって、会社のコンセプトや物件の良さが顧客に伝わるようなパンフレットを作ることは必須なのです。今回は、不動産業界の方が作るべきパンフレットや、その作り方について解説します。