食品表示法や薬事法も要確認!表示ラベル作成時の注意点
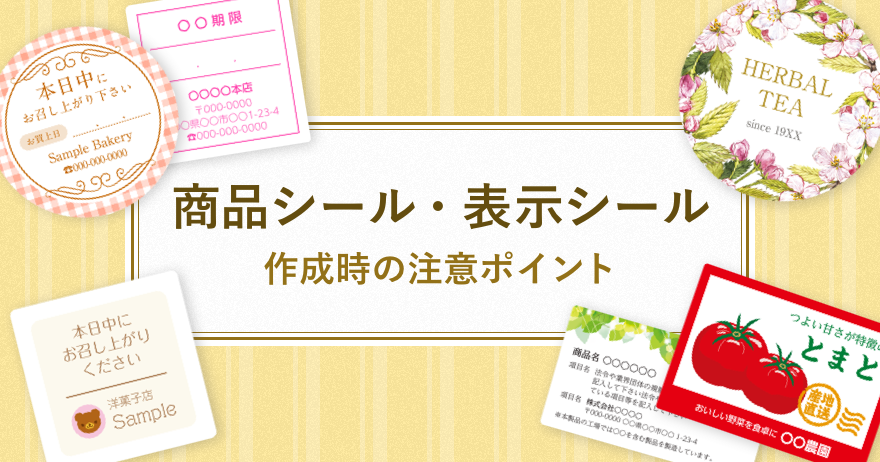
包装技術協会によれば、日本のパッケージ市場の規模は5兆6000億円で、41%が紙製品、31%がプラスチックや軟包装、17%が金属製品、2%がガラス製品、その他が11%です。
パッケージによって、商品の持ち運びが可能になり、ブランドも誕生しました。今回はパッケージに貼られている商品シールについて解説します。
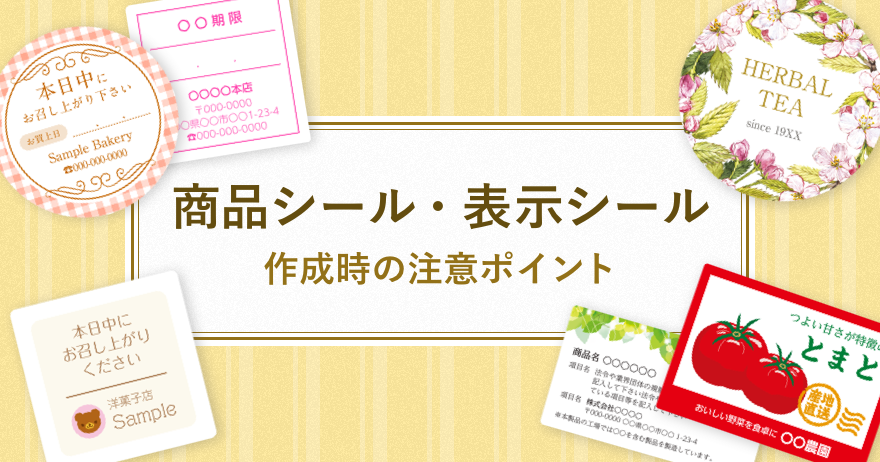
包装技術協会によれば、日本のパッケージ市場の規模は5兆6000億円で、41%が紙製品、31%がプラスチックや軟包装、17%が金属製品、2%がガラス製品、その他が11%です。
パッケージによって、商品の持ち運びが可能になり、ブランドも誕生しました。今回はパッケージに貼られている商品シールについて解説します。
食品や飲料、化粧品などの商品を販売する場合には、法律などに定められた基準で表示する義務が生じます。
具体的には「食品衛生法」が中心になりますが、食品アレルギー表示制度や、消費期限・賞味期限、製造者・加工業者の表示、乳業の表示基準などを表示しなければいけません。また、「JAS法に基づく品質表示」、米や、お酒、医薬部外品、化粧品などの適正表示に従うことも必要です。
いずれにしても、一般消費者向けに販売する場合は、製造者、あるいは販売者としての責任が生じますので、しっかりとラベル表示に取り組む必要があります。
一般消費者に向けて販売するのであれば、商品シールのデザイン制作にも力を入れる必要があります。
皆さんが、スーパーに入って、今まで食べたことのない商品を買い求める場合、何を参考にしますか。事前情報を持っていなければ、実は頼れるものは商品ラベルしかありません。消費者の皆さんにとって、商品シールは購買の第一要因になります。
競合商品などと、比較し、選択してもらうためには、消費者のニーズを反映し、それをデザインに展開する必要があります。シールのデザインもテンプレートを利用するのではなく、やはり、デザイナーを起用し、イラストレーターなどのデザインソフトで入力することによって幅が広がります。
特売や、イベント販売などでは、通常の商品シールに加えて、イベント告知や、特売をわかりやすく提示するシールを添付して、注意を引くこともあります。ワインなどでは、製造シリアルナンバーを印刷して、希少性をアピールするといった試みも行われています。
食品などでは、中身の特徴を表現する、カラーシリーズデザインをよく使います。特に、商品バラエティーが多い場合は、統一したデザインレイアウトやブランドマークで、独自性を訴求し、その上で色の使い分けを利用します。また色のこだわりにおいては、モノクロを利用することも効果的です。カラフルなデザインとは異なるクラシックな印象を与えることができます。
最近のプラスチックパッケージでは、プラスチックにはデザインを施さず、シュリンクラベル等によって、全体を覆って、フイルムならではの色彩表現を実現するなど、新しい利用方法も進んでいます。
また、商品には品質シールが貼られますが、最近は法律の変更で、表示内容が増加する傾向にあり、商品に占めるシールのサイズも拡大する傾向にあります。
商品シールを作成する際には、デザインだけでなく素材・加工にこだわることも重要です。同じデザインであっても、どのような素材・加工を選択するかで大きく印象が変わります。また使用環境に適した素材・加工を選択することで商品シールの状態を適切に保持することができます。
商品シールは中身を端的に表現しなければならないので、写真やイラストなどのデザインがよく使われます。写真やイラストを綺麗に再現するには、白地で色彩が鮮やかに表現されるアート紙やミラーコート紙などが多く利用されます。
冷蔵庫などに保管される商品や、水回りの商品には、紙素材ではなく、フイルム系のシールが利用されます。紙は水分に弱く、長く冷蔵庫などに保管すると変形したり、しわが寄ったりするのが一般的ですが、水に強い対水紙や合成紙なども開発されています。
接着剤も、一般的な使用では特に問題がありませんが、冷凍庫やレトルトなど、低温・高温の厳しい環境で使われる場合や、商品使用後にシールを剥がしたい場合、一般的な糊では密着しないざらざらした場所に使う場合などには、それぞれ特殊な糊が用意されています。
商品は、流通や保存の段階で、パッケージどうしの接触や、輸送途中のこすれなどに遭遇します。このような悪条件に対応するために、耐久性を考慮して、ラミネート加工を施すこともあります。
他にもエンボス加工をすることで、凹凸により立体感を演出することができます。また箔押し加工により金や銀の箔を貼り付け高級感を演出することもできます。
ラクスルではシールの加工の種類によって対応しているもの、していないものがございます(エンボス加工や箔押し加工については対応していません)。商品ページにてご確認ください。